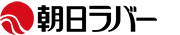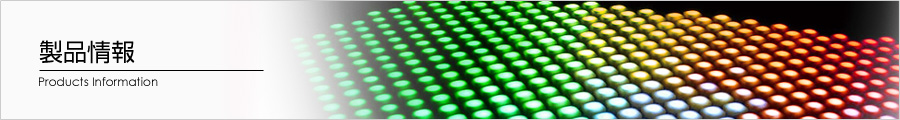LEDの色や明るさにばらつきが出る原因は?

従来光源ランプ(電球・蛍光灯など)に代わり、今や一般に広く普及しているLED照明ですが、時として色温度(色目)や明るさのばらつきが見られることもあります。
この記事では不具合の原因を考察した上で、対処法などを解説していきましょう。
LEDの基礎知識
LED照明は高効率で消費電力が低いとされていますが、どのような構造で、どんな特徴を持っているかを説明していきます。
LEDの種類と構造
汎用的に用いられるLEDには大きく分けて2種類ありますが、その構造はとてもシンプルです。
表面実装型LED(SMD)
一般的な形のLED照明として用いられるのがこのタイプです。小さな基盤に半導体素子を接合したものがLEDチップと呼ばれますが、このLEDチップに樹脂を封入して保護し、レンズを取り付けて指向性を高めています。
砲弾型LED
文字通り砲弾のような形状をしており、アノードとカソードの2つの端子を持っています。
屈曲率の高いドーム形レンズの中へ半導体素子を固定することで、効率の良い光源として古くから代表的なLEDとして用いられてきました。
LEDが発光する仕組み
次に、どのようにLEDが発光するのか?その仕組みを解説していきましょう。また現在のLEDは様々な色調を演出できますが、そこにはどんな工夫があるのでしょうか。
+と−の電気が結合することで発光する
まずLEDチップは2つの半導体によって成り立っています。「p型半導体」には+の性質を持つ穴(正孔)がたくさん空いていて、もう1つの「n型半導体」には電子(−の性質)がたくさん付着しています。
ここに順方向の電圧を加えると、正孔と電子は両方の半導体の接合面へ移動し結合します。すると互いが持っていた余分なエネルギーが光として放出され、光源として安定するといった仕組みです。
さまざまな色温度を演出する仕組み
LEDの黎明期には青色LEDや赤色LEDが実用化されていましたが、照明用としては普及されませんでした。そこで開発されたのが白色LEDです。
青色LEDの半導体素子に黄色の蛍光体を塗布することで、光を白色に変換するのです。一般的に普及しているLED照明のほとんどがこのタイプです。
また「赤色LED+緑色LED+青色LED」と組み合わせることで白色を表現するパターンもあります。より演色性を求める場合に用いられます。
「電球色」や「昼光色」といった色温度のパターンも、同様の方法で実現することができます。
LEDにばらつきが出る要素と原因

次にLED照明を設置した際、明るさや色にばらつきが出る要素や原因について解説していきます。明るさの低下やちらつきによって健康被害に繋がるケースもあるため、注意が必要です。
温度
LED照明の温度特性として、より低い温度であれば明るく発光し、温度が高くなるにつれて劣化が進み、短寿命となります。
特に夏場の野外では外気温の上昇もさることながら、LEDからの熱放射がうまくいかないと明るさの低下や色目の変化などを引き起こします。
もし外気温が50℃程度まで上がったと仮定すれば、LED内部の温度は70〜80℃まで上昇してしまうでしょう。こうなると一気に寿命が短くなってしまうことも考えられます。
製造工程
LED照明機器の中で、実際に光源となる半導体素子は重要な部品です。もし半導体素子に塗布される蛍光体にムラがあった場合、色温度や明るさにばらつきが出る可能性があるでしょう。
また半導体素子はシリコンやゲルマニウムといった物質が結晶を構成しているのですが、ごくまれに不純物が混入することがあるようです。これが原因となって結晶中に欠陥が生じ、発光が弱くなることがあります。
素子表面をカバーする保護膜などが設けられているケースですと、剥がれることで素子の不具合に繋がる可能性もあるところです。
大量生産される汎用品である以上、どうしても初期不良が起こるものですし、個体差によるイレギュラーは避けては通れないようです。
経年
LED照明にも寿命があり、おおむね20,000〜40,000時間とされています。[注1]
ですが、電球や蛍光灯と違って消灯した時が寿命ではありません。一般的には定格照度の70%程度まで明るさが落ちた時が寿命だとされています。
半導体素子そのものは半永久的に使える原理ですが、付属している基盤・蛍光体・樹脂といった部材が徐々に劣化していきます。
直管タイプをはじめLED照明の多くは、数十個の素子を集合させた製品ですから、素子が少しずつ点灯しなくなれば、暗くなっていきます。
とはいえ、人間の目は少しずつ暗くなっていく現象を認知できません。知らず知らずのうちに明るさが低下していき、やがて眼精疲労といった健康問題を引き起こすことに繋がる可能性があります。
[注1]経済産業省 「電球類及び照明器具の現状について」
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/shomei_kigu/pdf/2016_01_03_00.pdf
LED照明を並列に取り付けた場合の不具合

次に取付方法が誤っていたケースでの不具合です。LEDを発光させる際に加える順方向電圧をVFと呼びますが、もしLED照明器具を並列に繋いだ場合、片方が明るくて、もう片方が暗いという現象が起きる場合があります。
同じ仕様の器具だったとしても、部品の劣化やばらつきによる個体差は少なからずあるもの。そのため片方にだけ多く電流が流れることになります。
LEDのばらつきを抑えるには?
明るさや色温度のばらつきの原因を解説してきたところで、次にばらつきを抑える方法を解説していきましょう。
安定した品質や技術を持つメーカーから購入する
まずは、海外製の安価な製品ではなく、安定した品質や技術を持つメーカーからLED照明を購入することが、品質のばらつきを抑えることができる方法のひとつです。
量産品であっても安定した品質が保証されていれば安心ですし、万が一イレギュラーがあったとしても、きちんと保証やアフターフォローが期待できるからです。
またLEDは温度上昇による不具合も多いため、放熱対策などの技術をメーカー側が備えていることも重要です。信頼のおける製品仕様書やデータシートをしっかり提示できるのであれば、より安心でしょう。
朝日ラバーでは明るさや色温度のばらつきを抑えた高品質LEDを提供しています。
https://www.asahi-rubber.co.jp/products/led/index.html
設置環境に見合った器具選定を
LED照明には寿命や全光束といったカタログ数値の他に、使用温度という項目があります。これは「〇℃〜〇℃までなら能力を発揮できます」といった指標です。
もし室内向けLED照明を野外に設置した場合、夏場ですと熱放射ができず、能力を発揮できないどころか寿命が短くなってしまう可能性があります。
それぞれの使用環境に合ったLED照明を選択することで、思わぬ不具合が回避できるのです。
経年劣化への対策
LED照明の寿命はおおむね決まっており、その時期が来れば交換のタイミングとなります。設置した年月日をあらかじめ記録しておき、一日の稼働時間×稼働日数から計算して、適宜なリプレイスを心掛けたいところです。
想定寿命を過ぎている場合、「まだ明るい」と感じていても、実際の照度は下がっているケースがほとんどですから、思い切って交換することが環境の改善へと繋がることでしょう。
取付け時に並列で繋がないこと
LED照明を取り付ける場合、やはり並列に繋ぐことは不具合を伴います。先述の通り、同じ仕様の器具でも個体差があるためにVFが一定しないからです。直列で取り付けることが望ましいでしょう。
まとめ
LED照明の色や明るさにばらつきが出る現象は、多くのシーンで見受けられる問題です。しかし原因を明確にすることで不具合を防ぎ、照明環境の改善に繋がる対処法も見えてくるでしょう。
LED照明が広く普及した現在は、数えきれないほどの製品が出回っていますが、目的や用途に合った照明を選ぶとよいでしょう。
その他の記事